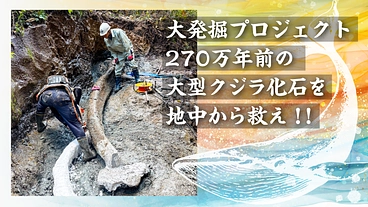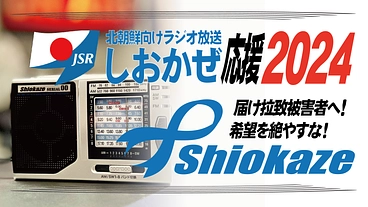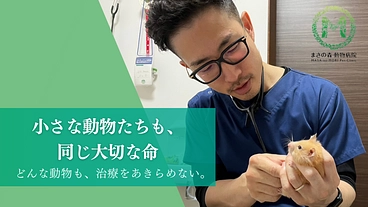このプロジェクトでは継続的な支援を募集しています
明日を担う伝承者の養成を共に支える│国立劇場養成所サポーター募集

マンスリーサポーター総計
【活動のご報告】~部外研修・都内史跡見学~
日ごろより国立劇場養成所をご支援くださり、誠にありがとうございます。
国立劇場各館で行われている伝承者養成事業について、皆様にもっと知っていただけますよう、日々の研修の様子などをご紹介してまいります。
今回は、部外研修の一環として実施している「都内史跡見学」についてお届けいたします。
~部外研修・都内史跡見学~
研修分野を跨いで行う部外研修では、歌舞伎や落語をはじめとする数多くの伝統芸能にとって重要な題材となった町を訪れ、そこで営まれてきた文化や生活への理解を深めています。
今回の舞台は、上野・根津・谷中。
昨年11月、お天気に恵まれた12名の研修生たち(歌舞伎俳優・歌舞伎音楽・大衆芸能)は、演芸評論家の瀧口雅仁先生の案内で江戸の町の面影が残る都内の史跡を見学しました!
・まずは、座学!

出発の前に、講師の瀧口先生より江戸時代と伝統芸能の関係についてご講義いただきました。
盛り上がった座学の時間は、あっという間。
いざ、都内史跡見学へ出発です!
①上野恩賜公園内
(西郷隆盛像→彰義隊の墓→天海僧正毛髪塔→秋色桜の碑→蜀山人の碑→清水観音堂→不忍池→擂鉢山古墳→時の鐘→上野大仏パゴダ)
さっそく、上野恩賜公園へ移動した研修生たち。
狂歌三大家と評される大田南畝の「蜀山人の碑」。
「一めんの花は碁盤の 上野山 黒門前に かかるしら雲」の歌が刻まれています。
桜を碁盤、黒門としら雲を白黒の碁石に見立てたこの一首から、
江戸時代の方位や寛永寺が建立された経緯について学びました。
当時から、上野の桜は名所だったそう...
満開の桜が碁盤のように咲く江戸の風景に思いを馳せる研修生たちでした。

寛永寺境内の「清水観音堂」。
京都の清水寺と同じ舞台造りだそうです。
円を描いた「月の松」は、新たに復元されたものですが、歌川広重の『名所江戸百景』に描かれています。研修生は、浮世絵と比較しつつ、今と変わらない景色に感動していました!
続いて、寛永寺境内の「時の鐘」へ。
松尾芭蕉が詠んだ「花の雲 鐘は上野か 浅草か」の句で知られています。
元禄以降、江戸の町の拡大に伴い、上野を含む9箇所に鐘が置かれ、前の鐘の音を聞いてから順番に鳴らしていたそうです。

・上野から谷中方面へ
(旧因州池田屋敷表門→博物館動物園駅(跡)→吉田屋酒店(台東区立下町風俗資料館敷設展示場)→自性院→大圓寺/さんさき坂→全生庵)
上野から谷中へ足を進め、江戸時代から代々酒屋を営んでいた「吉田屋酒店」を見学しました。
実際に使われていた帳場机やそろばんを眺めながら、番頭の商いの様子を想像します。
研修生は、一斗瓶の大きさに驚いていました!

幕末の幕臣、山岡鉄舟が建立した谷中「全生庵」では、落語家の初代三遊亭圓朝と女流義太夫の初代竹本住之助の墓所をお参り。
その前の「三崎坂(さんさきざか)」は、歌舞伎でもお馴染みの圓朝作『怪談牡丹燈籠』の舞台にもなったそうです。

・終点 谷中
(観音寺→谷中霊園/天王寺→谷中ぎんざ・夕やけだんだん)
いよいよゴール目前‼️
谷中の代表的スポットの1つである「観音寺」は、赤穂義士ゆかりのお寺です。
瓦と粘土を交互に積み重ねて防火・防災性を高める「築地塀(ついじべい)」は、国の登録有形文化財に指定されています。
研修生は、塀と背比べしながら街並みを撮影していました。

そして…ついにゴールの谷中ぎんざに到着!
ご紹介しきれない場所を含め、約半日巡りました。

今回の研修は、現代を生きる研修生にとって、歌舞伎や落語の舞台となった土地や名所を実際に訪ね、作品背景の理解を深める良い機会となりました!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
今後とも、国立劇場養成所にご支援・ご声援をよろしくお願い申し上げます。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
国立劇場養成課の公式X(旧Twitter)(@kokuritsu_yosei)・Instagram(@kokuritsu_yosei22)・
TikTok(kokuritsu_yosei22)でも、随時研修の様子をご紹介しております。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―